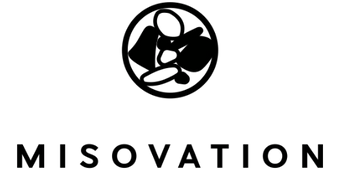【MISOTIMES】名前の由来は五つの“徳”。こだわりの若狭五徳みそ / JA福井県小浜加工センター

日本各地の味噌蔵さまを深堀りしていくMISOTIMES。
今日は「若狭五徳みそ」を製造されている、JA福井県小浜加工センターの工場長 清水様にお話を伺いました。
|
目次 |
名称でもある「五徳」の由来とは

MISOVATION「若狭五徳みそとはどのような味噌なのですか?」
清水様「5つの徳が名前の由来になっています。①郷土の味を伝える徳(地元の大豆、米使用)②自然の力を利用して作る徳(天然熟成)③ゆっくり時間をかけて作る徳(6ヶ月以上熟成)、④塩分控えめ11%程度である徳、⑤安全安心な無添加である徳。この五徳の基本理念をもとに丁寧につくっています。大豆と麹の割合が1:2のためやや甘口です。塩はにがりを含む上質な塩を使用しており、まろやかな舌触りが特徴ですね。」
MISOVATION「とてもこだわりの詰まった味噌なのですね。販路はどのようになっていますか?」
清水様「地域のJA直売所、道の駅、生協で販売しています。また、地域の学校給食にも味噌を使用いただいています。」
姉妹都市の奈良市から作り方を学んだ

MISOVATION「味噌作りをはじめたきっかけを教えて下さい。」
清水様「味噌は1200年前に中国から遣唐使によって奈良に伝えられたと考えられています。昭和60年頃、小浜市の姉妹都市である奈良から当時奈良で盛んに行われていた"味噌作り講習会"を教えてもらい、そこから小浜市でもみそ会館にて講習会をはじめました。その後、JAが講習会を引き継ぐ形となったのですが、平成元年にはこれまで講習会で教えていた五徳みそを商品化することになり、現在に至っております。」
MISOVATION「もともとは奈良で有名な味噌だったのですね!講習会から長い歴史を経て商品化に至ったのも印象的です。」
味噌づくり講習会を通じてファンが増加

MISOVATION「味噌づくり講習会は今も開催されているのですか?」
清水様「はい。今でも年間50回ほど開催しており、700-800名の方に味噌づくりを体験いただいています。期間は毎年11月〜3月です。昔は市内(福井県小浜市)の方が多く参加されていたのですが、今は市外・県外の方も増えてきましたね。近隣の市ですと敦賀市、県外ですと滋賀の今津や京都の舞鶴から参加される方もいます。」
MISOVATION「年間700-800名...!凄い規模ですね。」
清水様「コロナの時は開催をSTOPしたのですが、無事再開できてよかったです。実は大規模な宣伝はしておらず、県内のJAなどにチラシを置くくらいで、集客のメインは口コミですね。4人1組での実施になるので、ファンの方が周りの方に"一緒に参加しよう"と広めてくれているのだと思います。最近では小学校での開催をはじめました。非常に反応も良く、食育として取り組む意義もあると思っています。小学校だけでなく公民館での開催など、開催場所を増やしていきたいです。」
MISOVATION「講習会を通じたコミュニティ形成を長く続けているからこそ、多くの方に愛されているのだと感じました。貴重なお話をありがとうございました。」
〜〜〜
いかがでしたでしょうか?
これからもMISOVATIONでは日本各地の味噌蔵様の味噌造りに想いやこだわり、魅力などを発信していきます。